
| 社号 | 等乃伎神社 |
| 読み | とのき / とのぎ |
| 通称 | |
| 旧呼称 | 天神社 等 |
| 鎮座地 | 大阪府高石市取石 |
| 旧国郡 | 和泉国大鳥郡富木村 |
| 御祭神 | 天児屋根命 |
| 社格 | 式内社、旧村社 |
| 例祭 | 10月5日 |
等乃伎神社の概要
大阪府高石市取石に鎮座する式内社です。
当社の創建は詳らかでありませんが、中臣氏の一族である「殿来氏」が祖神を祀ったと考えられています。
『新撰姓氏録』和泉国神別に天児屋命の後裔であるという「殿来連」が登載されており、この氏族が当社を奉斎したと思われます。
社伝では『続日本紀』天平勝宝四年(752年)の条に見える「中臣殿来連竹田売」なる人物が当地に居住して奉斎したとし、「藤原武智麻呂」や「恵美押勝(藤原仲麻呂)」が相次いで来住したと伝えています。
あくまで伝承に過ぎませんが、近隣に「大鳥大社」など有力な中臣系の神社があり、当地一帯が中臣系氏族の重要な根拠地の一つだったことは想定して良さそうです。
一方で当地における古伝として、『古事記』に次のような記事があります。
『古事記』(大意)
仁徳天皇の御代、兔寸(トノキ)河の西に一本の巨樹があり、朝日に当たればその陰が淡路島を、夕日に当たればその陰が高安山を越えるほどであった。
この巨樹を伐って船が造ったところ、この船はとても俊足で、「枯野(カラノ)」と名付けられた。この船で朝夕に淡路島の泉の水を運んで献上した。
ここに船が壊れてしまい、これで塩を焼き、焼け残った木で琴を作ったところ、その音は七里まで響いた。
このように当社付近を流れる川の西にとてつもなく巨大な木があり、これで船が造られたとあります。
この船の名前「枯野」は「カヌー」と同根であるとする説もあり、大変興味深い伝承です。
一方で、この巨樹の陰が淡路島や高安山に届いたとする点に着目し、当地を周囲の山から太陽の動きを計測することで季節を知る「日読み」の地だったとする説もあります。
なお、同様の記事は『播磨国風土記』逸文にもあり、その巨樹は当地でなく明石駅にあり、造られた船の名は「速鳥」であると記されています。
『古事記』と『播磨国風土記』逸文の記述を比較したとき、当地はともかく明石を日読みの地とするのはいささか厳しいでしょう。
一方で両地に同様の伝承があることは、材木の供給や淡路島との交通網等の痕跡である可能性があるのかもしれません。
大歳神社
等乃伎神社には式内社「大歳神社」を合祀しています。御祭神は「大歳神」。
元々は等乃伎神社の南西1.5kmほど、高石市西高取(旧・市場村)の清高小学校の敷地内に鎮座していましたが、明治四十二年(1909年)に神社合祀政策により等乃伎神社に合祀されました。
当社の創建・由緒等は詳らかでありません。江戸時代中期の地誌『和泉志』によれば当時「天神」と呼ばれていたようですが、その他詳しいことは全く不明です。
境内の様子


境内入口。住宅地の中にありますが、境内は鬱蒼とした森になっています。
一の鳥居は西向きに建っています。

一の鳥居をくぐるとその先に二の鳥居が西向きに建っており、石畳の参道は二の鳥居をくぐったところで折れ曲がっていて升形状になっています。


二の鳥居をくぐったところに「祓岩」なる岩石があり、社殿への参拝の前に穢れを祓う場合はここにお参りするよう案内されています。
かなり珍しいものですが、奈良県などの神社ではしばしば参拝前に祓戸神に参拝することで穢れを祓う例があり、それと同様のものと言えるかもしれません。


参道の升形状になっているところに手水舎があります。

升形状の参道の先に広い空間があり、その奥の玉垣で仕切られたやや小高くなった空間に社殿が西向きに並んでいます。


拝殿は銅板葺の平入の入母屋造りに唐破風の向拝の付いたもの。
本殿は塀で囲われておりよく見えません。本殿の形式は三間社流造のようです。


拝殿前の狛犬。花崗岩製で、古めかしさが感じられます。
当社には多くの狛犬があるため全てを紹介することはできませんが、個性的な顔立ちの狛犬もあり、これらを眺めるのも当社の参拝の醍醐味と言えそうです。


本社社殿の右側(南側)に「稲荷社」が西向きに鎮座。
拝所の奥に本瓦葺の一間社春日造の社殿が建っています。

さらに境内南側の森に「祓宮」が西向きに鎮座。御祭神は「天御中主神」。
かなり真新しい社殿で、銅板葺の流見世棚造となっています。なお以前は平入寄棟造の石祠でした。
天地開闢の際に生まれたとされる「アメノミナカヌシ」は水天宮や妙見宮が明治の神仏分離の際に祭神を替えた結果として祀られる例が見られますが、そうでないのに祀られるのは珍しいことです。
当社でどのような経緯で祀られたのかは不明。

境内社のある南側の空間は樹木が密生し森になっています。
流石に『古事記』に描かれているような高安山や淡路島まで陰の届く巨樹はありませんが、当社の神域としての古さを感じるのに十分な大きな木もあります。

境内北側にある授与所。
当社は非常に多彩なお守りを授与していることでも有名で、授与所には多くの見本が展示されています。珍しいお守りを求めて全国から参拝客が訪れているとも。


当社の付近には若干ながら古い町並みも残っていました。
御朱印
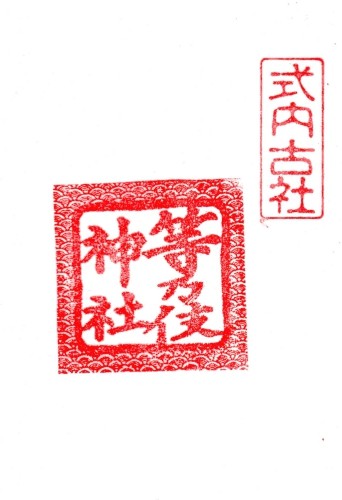
由緒
案内板
式内 等乃伎神社縁起
『和泉名所図会』
地図
